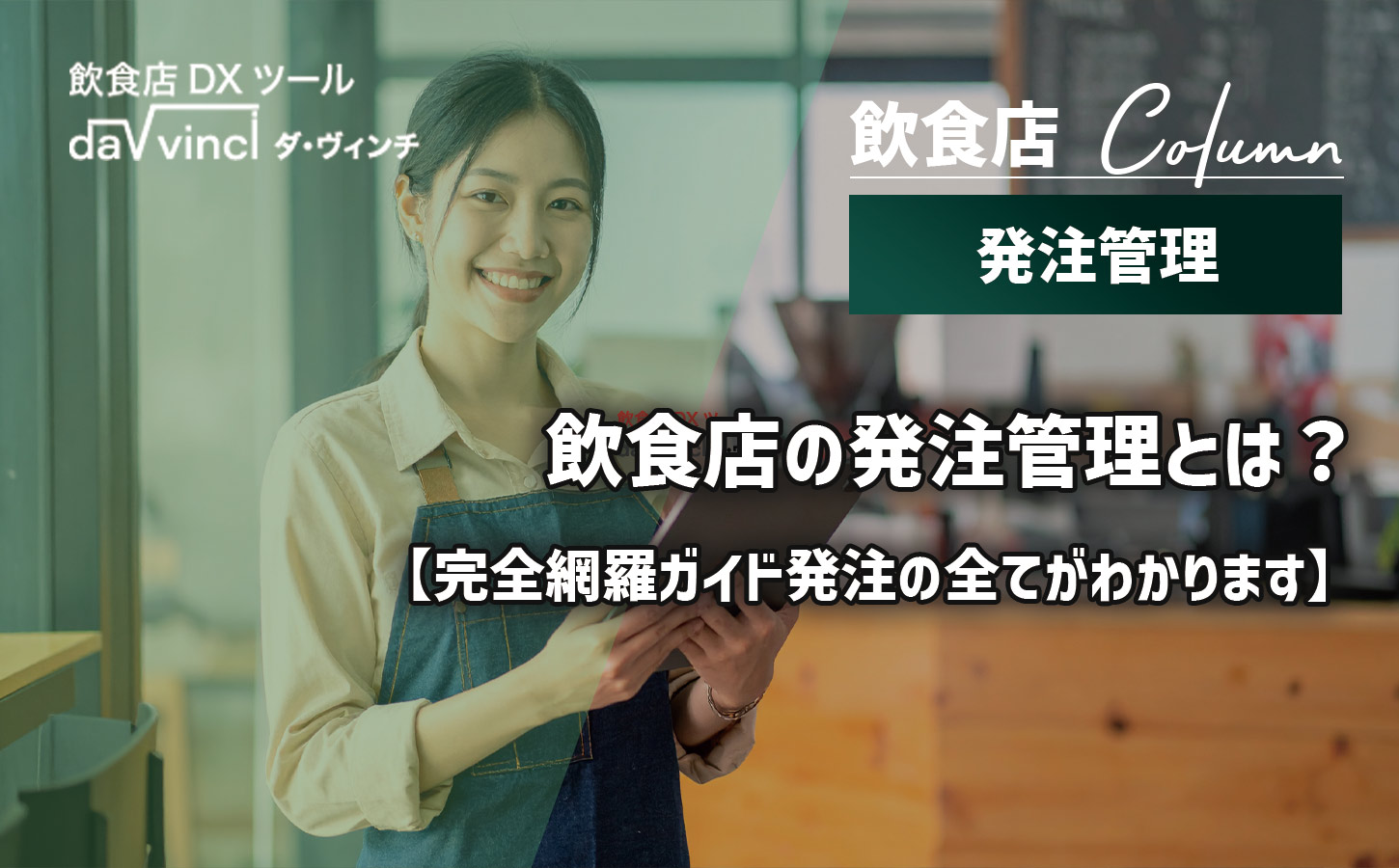「また在庫が合わない…」 「あのアルバイト、ちゃんと発注できるだろうか?」 飲食店の経営者や店長の皆様なら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。 発注ミスは、単に食材を無駄にするだけでなく、欠品による […]
飲食店の発注ミスを防ぐ方法|原因別の対策と仕組み化のコツを解説!
2025/08/20
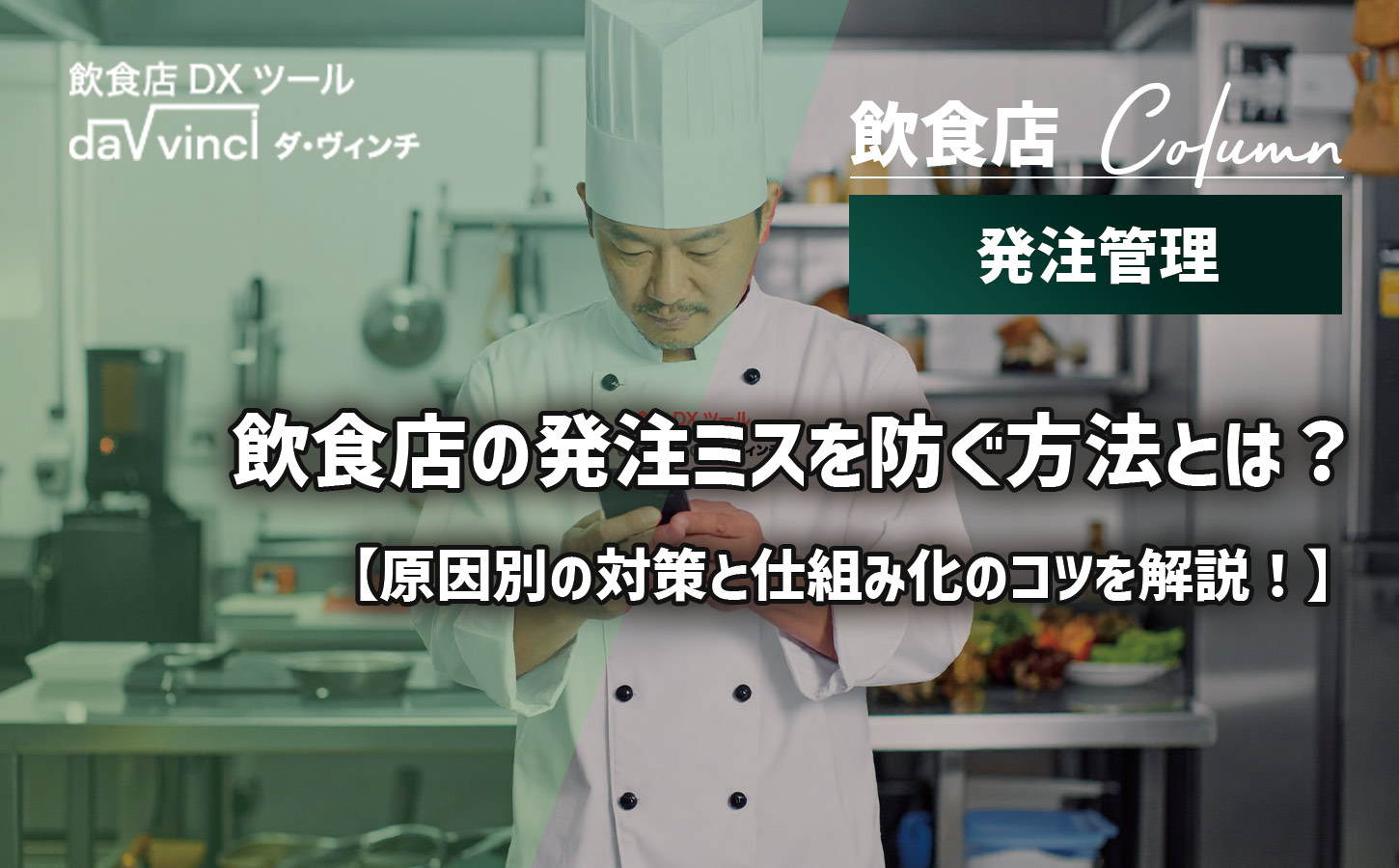
「また在庫が合わない…」
「あのアルバイト、ちゃんと発注できるだろうか?」
飲食店の経営者や店長の皆様なら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。
発注ミスは、単に食材を無駄にするだけでなく、欠品による機会損失や顧客満足度の低下、さらにはスタッフの精神的な負担にも繋がる深刻な問題です。
この記事では、注意喚起や精神論に頼るのではなく、誰がやってもミスが起こらない「仕組み」で発注ミスを解決する方法を徹底解説します。
明日からすぐに実践できる具体的な対策から、ITツールを活用した根本的な業務改善まで、あなたの店の利益と安定を守るためのヒントが満載です。
この記事を読めば、発注業務のストレスから解放され、より創造的な店舗運営に集中できるようになるでしょう。
なぜ繰り返す?「うっかり」で済まされない発注ミスの3つの根本原因

発注ミスが頻発すると、「スタッフの確認不足だ」「もっと注意してくれれば」と、個人の資質に原因を求めてしまいがちです。
しかし、ほとんどの場合、ミスは個人の問題ではなく、店舗の運営体制や業務フローといった「仕組み」に根本的な原因が潜んでいます。
ここでは、多くの飲食店が陥りがちな3つの根本原因を掘り下げて見ていきましょう。
原因を正しく理解することが、効果的な対策への第一歩となります。
原因1:個人の経験と勘への依存(認知バイアス)
「週末はいつも混むから、このくらいだろう」
「昨日はこのメニューがよく出たから、多めに仕入れておこう」
こうした経験豊富なスタッフの「勘」は、時に大きな武器となりますが、発注ミスを引き起こす原因にもなり得ます。
これは「認知バイアス」と呼ばれる心理的な思い込みの一種です。
例えば、直近の売上データに過度に依存してしまったり(利用可能性ヒューリスティック)、過去の成功体験から判断を誤ったり(確証バイアス)することがあります。
ベテランスタッフほど、自身の経験への過信から確認作業を怠り、予期せぬ需要の変動に対応できなくなるケースは少なくありません。
原因2:スタッフ間の情報共有不足
発注ミスは、スタッフ間のコミュニケーション不足から生じることも非常に多いです。
ホールスタッフが把握している「週末の予約状況」や「特定のコースメニューの出数」といった情報が、発注担当者に正確に伝わっていなければ、適切な発注はできません。
また、キッチンスタッフが気づいた「特定の食材の傷みが早い」といった情報共有も重要です。
「言ったつもり」「聞いたはず」といった口頭での曖昧な情報伝達や、情報が特定のスタッフで止まってしまう状況は、需要予測のズレを生み、過剰在庫や欠品のリスクを高めます。
原因3:非効率なアナログ業務とチェック体制の欠如
閉店後の疲れた頭で、手書きの発注リストを片手に業者へ電話やFAXで発注する。
多くの飲食店で見られる光景ですが、こうしたアナログな業務フローにはミスを誘発する危険性が潜んでいます。
走り書きのメモは判読しづらく、電話での口頭注文は聞き間違いや言い間違いのリスクが常に伴います。
さらに、発注作業が特定の担当者一人に任され、他の誰もチェックしない「属人化」した状態は非常に危険です。
その担当者が休んだり、退職したりした場合、店の発注業務が立ち行かなくなる可能性さえあります。
まずはココから!明日から実践できる発注ミス防止の4ステップ

根本的な原因が分かったところで、次は何をすべきでしょうか。
大がかりなシステム導入の前に、まずは現在のオペレーションを見直すことから始めましょう。
ここでは、特別なコストをかけずに明日からすぐに実践できる、発注ミス防止の4つのステップをご紹介します。
ステップ1:発注ルールを「見える化」する
まず、発注に関する情報を「誰が見ても分かる」状態にすることが重要です。
業者ごとに異なる発注方法や締め切り時間を、担当者の頭の中だけに留めておくのはやめましょう。
以下のような一覧表を作成し、バックヤードなどスタッフ全員が見える場所に掲示するだけでも効果は絶大です。
| 業者名 | 主要取扱品目 | 発注方法 | 連絡先/URL | 締め切り時間 | 備考(最低ロットなど) |
|---|---|---|---|---|---|
| A青果 | 野菜全般 | 電話 | 03-XXXX-XXXX | 前日 17:00 | |
| B精肉店 | 豚肉・鶏肉 | FAX | 045-XXX-XXXX | 2営業日前 15:00 | |
| Cサプライ | 乾物・調味料 | Webシステム | https://… | 毎週水曜 12:00 | 5,000 円以上で送料無料 |
| D酒店 | 酒類全般 | 専用アプリ | 納品希望日の前日 24:00 |
このように情報を整理することで、担当者が不在の際でも他のスタッフが対応できるようになり、業務の属人化を防ぐ第一歩となります。
ステップ2:在庫管理の基準(発注点)を明確にする
「在庫がこれくらいになったら発注する」という基準を食材ごとに具体的に決めて共有しましょう。
これにより、「まだ大丈夫だと思った」「もう無いとは思わなかった」といったスタッフ間の認識のズレを防ぐことができます。
特に経験の浅いスタッフでも判断に迷わないよう、視覚的に分かりやすくするのがコツです。
- 棚に線を引く: 在庫棚に「このラインを下回ったら発注」という印のテープを貼る。
- 写真付きマニュアル: 適正在庫と発注点の在庫量を写真に撮り、ラミネートして棚に貼っておく。
- 容器で管理: 1 日の使用量ごとに小分けの容器に移し、「残り2容器になったら発注」といったルールにする。
こうした簡単な工夫で、誰でも同じ基準で在庫状況を判断できるようになります。
ステップ3:発注確認のチェックリストを作成・徹底する
人間の記憶や注意力には限界があります。
思い込みや確認漏れによるミスを防ぐためには、機械的なチェックの仕組みが不可欠です。
パイロットがフライト前に必ずチェックリストを確認するように、発注業務にもチェックリストを導入しましょう。
| チェック項目 | 確認内容 | チェック欄 |
|---|---|---|
| 発注先 | 発注先の業者名は正しいか? | ☐ |
| 品目 | 品名、規格(サイズ、産地など)は正しいか? | ☐ |
| 数量 | 発注する数量は適切か?(在庫数と需要予測を確認) | ☐ |
| 単位 | 単位(個、kg、パック、ケースなど)は正しいか? | ☐ |
| 単価 | 発注単価に変動はないか? | ☐ |
| 納品日 | 納品希望日は正しいか?(定休日と重なっていないか) | ☐ |
このリストを使って指差し確認を徹底するだけで、「うっかりミス」を劇的に減らすことができます。
ステップ4:複数人でのダブルチェック体制を構築する
どんなに注意深く作業しても、一人の人間がミスを完全になくすことは困難です。
そこで、発注担当者が作成した発注書(またはWeb画面)を、注文を確定する前にもう一人のスタッフが確認する「ダブルチェック」の体制を整えましょう。
この時、大切なのは「ミスを責めない」という文化を作ることです。
ミスを指摘することは、個人への非難ではなく、チームで店のリスクを管理するための重要なプロセスです。
お互いに確認し合える風通しの良い職場環境(心理的安全性)が、結果として店舗全体のミス削減につながります。
【根本解決】属人化から脱却し利益を生む「仕組み」の作り方

ここまでのステップで、日々のオペレーションにおけるミスは大幅に削減できるはずです。
しかし、より安定した店舗運営を目指し、発注業務の負担から根本的に解放されるためには、個人のスキルに依存する体制そのものから脱却する必要があります。
テクノロジーを活用して「誰がやってもミスが起きない」、さらには「利益体質につながる」仕組みを構築する方法を見ていきましょう。
これは単なるミス防止策ではなく、未来の利益を生み出すための戦略的な投資です。
データで需要を予測する:勘に頼らない発注へ
これまでの経験と勘に頼った発注から、データに基づいた「データ駆動型」の発注へと移行しましょう。
多くの飲食店で導入されているPOSシステムには、日々の売上データが蓄積されています。
過去の売上データに加えて、天気予報、曜日、近隣のイベント情報などを統合的に分析し、需要予測を行うことで、廃棄ロスの削減や発注業務にかかる時間を短縮することができます。
【導入事例】発注も経営も改善!飲食店特化DXツール「ダ・ヴィンチ」の実力

「データ活用や自動化と言われても、何から手をつければいいのか…」
そうお考えの経営者様も多いでしょう。
仕組み化の具体的な解決策として、ここでは飲食店に特化したDXツール「ダ・ヴィンチ」をご紹介します。
「ダ・ヴィンチ」は、これまで解説してきた課題解決をワンストップで実現し、発注業務の効率化はもちろん、店舗全体の経営改善をサポートする強力なパートナーです。
「ダ・ヴィンチ」が解決する現場の課題とは?原価管理から日次PLまで
「ダ・ヴィンチ」は、一般的な会計ソフトやPOSシステムとは一線を画す、飲食店経営に特化した多彩な機能を搭載しています。
発注ミス防止に直結する機能から、経営判断を加速させる機能まで、現場の課題を解決する具体的な中身を見ていきましょう。
| 主要機能 | 具体的なメリット・効果 |
|---|---|
| 原価管理 | 過去の売上データに基づき、AIが発注量を自動提案。勘に頼らない発注で食材ロスを平均15%削減。 |
| 売上管理 | 顧客の属性や購買履歴を分析し、ニーズに合ったメニュー開発を支援。顧客単価15%向上の実績も。 |
| 勤怠管理 | 従業員のスキルに基づきAIがシフトを自動作成。人件費を最適化し、10%削減に貢献。 |
| 予実管理 | 売上・原価・人件費を自動集計し、日次PLをリアルタイムで作成。経営状況を即座に把握し、迅速な意思決定を可能に。 |
実際に焼肉店チェーンの株式会社デイドリームでは、「ダ・ヴィンチ」の導入により、これまで手作業で行っていた事務作業を50%削減することに成功しています。
これは、発注業務の効率化だけでなく、店舗運営全体の生産性が向上したことを示す好事例と言えるでしょう。
発注以外にも応用可能!店舗全体のミスを減らすヒント

これまでご紹介してきた発注ミスを防ぐための「仕組み化」の考え方は、オーダーミスや調理ミスといった、店舗で起こりがちな他のミスを減らすためにも非常有効です。
例えば、以下のような応用が考えられます。
- オーダーミスの防止: 注文を受ける際の復唱ルールをチェックリスト化する。ハンディターミナルやセルフオーダーシステムを導入し、手書き伝票を廃止する。
- 調理ミスの防止: レシピを写真付きでマニュアル化し、誰でも同じ品質で作れるようにする。キッチンディスプレイを導入し、口頭での注文伝達をやめる。
重要なのは、ミスが起きた際に個人を責めるのではなく、「なぜそのミスが起きたのか」を仕組みの観点から分析し、チーム全員で再発防止策を共有することです。
こうした文化が、店舗全体のオペレーション品質を高めていきます。
まとめ:発注ミス防止は守りではなく、攻めの経営改善

本記事では、飲食店の深刻な課題である発注ミスについて、その根本原因から、明日からできる対策、そしてテクノロジーを活用した根本解決策までを解説しました。
| 対策レベル | 具体的な方法 |
|---|---|
| レベル1:すぐできる | – 発注ルールの見える化 – 発注点の明確化 – チェックリストの作成 – ダブルチェック体制 |
| レベル2:仕組み化 | – 売上予測による需要予測 – 飲食店特化DXツールの導入 |
発注ミスを防ぐことは、単に食材ロスやコストを削減する「守り」の施策ではありません。
業務効率化によって生まれた時間や人材という貴重な経営資源を、接客品質の向上や新メニュー開発といった「攻め」の活動に再投資するための、重要な経営改善の一環です。
まずは、この記事で紹介した「ステップ1:発注ルールの見える化」や「ステップ3:チェックリストの作成」から始めてみませんか。
その小さな一歩が、あなたの店舗をより強く、より利益の出る体制へと変えるきっかけになるはずです。
発注ミスの根本対策に──飲食店特化DXツール「ダ・ヴィンチ」で業務を見える化
属人化による発注ミスを本気で無くしたいなら、クラウド型業務管理ツール「ダ・ヴィンチ」の導入が有効です。電話・FAX・紙に頼らず、取引先ごとの発注ルールや履歴を一元化。発注業務の流れを整えることで、誰が担当してもブレない体制が整います。
- 発注・仕入・棚卸がワンシステムで連携し、手間を削減
- 商品ごとの発注履歴や在庫数をクラウドで一括管理
- 操作は2タップで完結。現場スタッフでも直感的に使える)
発注業務の属人化やミスにお悩みの方は、da Vinciの発注管理機能についてお気軽にご相談ください。
この記事を書いたライター

ダヴィンチ編集部
「データ入力」から「日次PL」、そして「経営の打ち手」まで、ワンストロークで。
ダ・ヴィンチは、飲食店経営の現場課題を骨の髄まで知るオーナーたちが開発した、現場目線の経営支援ツールです。
飲食店特有の煩雑な作業や“勘どころ”を最短ルートでデジタル化し、日々の売上・原価・人件費などのデータを入力するだけで、毎日のPL(損益計算書)が自動作成され、即座に経営判断に活かせます。
“現場の感覚”と“データ”を融合させ、現場力を最大化するためのツール、それが ダ・ヴィンチ です。詳しくはこちら